お客様によってはしっかりした提案依頼書がある場合もありますが、多くの場合は提案を行うにあたってお客様に対する何らかのヒアリングを行うことになると思います。この記事では提案に先立ってヒアリングについてお話したいと思います。
すでに業者の選定は始まっている
提案活動において勝負所はもちろん「提案プレゼン」ということになりますが、その前のヒアリングの段階でもすでに業者選定は始まっています。即ち「的外れなヒアリング」を行ってしまえば受注レースにおいて一歩も二歩も後退すると認識してください。
調べて判ることは聞かない
お客様のWebサイトや会社四季報などで入手可能な情報についてヒアリングしてはいけません。例えば・・・
・ユーザー数は何人か?(注1)
・支店・営業所はどのぐらいあるのか?
・海外拠点の有無
・営業時間
などなど、調べればすぐわかるようなことを聞いていてはお客様は「コイツ真剣にやってないな」と思われてしまいます。
注1:ユーザー数について
ユーザー数については従業員数からある程度予測がつきます。もちろん従業員全員が使用するわけではないシステムの場合もありますし、Webなどに公開されている従業員数に加えて派遣社員やアルバイトの人が加わるケースもありますが。ある程度は予測できるはずです。
いただいた回答の活用方法について示す
各ヒアリング項目の回答を「どのように提案内容に生かすのか?」をできるだけ伝えましょう。このことには以下のメリットがあります。
・ 提案する内容についてある程度シナリオが作れていることをご理解いただける
・ 回答の利用イメージを伝えることでより適切な回答を期待できる
ヒアリング項目には回答例や仮設を添える
ヒアリング項目については理解できたとしても、文書があまり得意でないお客様の場合はなかなかこちらの欲しい回答が返ってこない場合もあります。そのようなことを回避しつつご担当者の負担を軽減するためには回答例やこちらで考た仮説を添えます。
提案に伴うヒアリング項目について大した調査もせずに思いつくままにあれこれヒアリング項目を挙げてくる人もいますが、そのようなアプローチではまず優良案件は受注できないと肝に銘じてください。
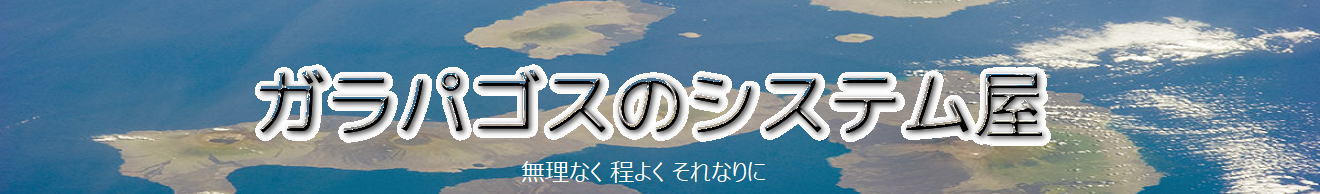



コメント