オフィスソフトに関するスキルの必要性については以下の記事で書きました。
オフィスソフトのスキルは必要?
さて、オフィスソフトスキルのの習得についてですが、別に皆さんがオフィスソフトのインストラクタになるわけではないので、必要な操作のみ習得すればよいとお考えだと思います。(この辺りが「ある程度」ですね)
そうはいってもそれそれのオフィスソフトには星の数程機能があるので、どこまで覚えたらいいかというのも悩むところだと思います。そこで今回は私が考えるオフィスソフトに関する必要なスキルについてお話したいと思います。
(以降は、基本的に「MS Office」を前提とさせていただきますね)
オフィスソフトの使い分け
オフィスソフトスキルをどうやって習得するかということですが、まずはオフィスソフトの使い分けについて考えたいと思います。もちろんお客様やプロジェクトのルールで自由にオフィスソフトを選択できない場合もありますので「あくまで参考」ということでご理解下さい。
・表計算ソフト(Excel)
表計算ソフトをメインのドキュメントツールと位置付け、設計書でもパラメータシートでも何でもかんでも表計算ソフトで作成するというお客様もいらっしゃいます。
でも、表計算ソフトは元々は表を作ったり表内で自動計算をするためのソフトです。なので表形式でドキュメントを作成する場合(パラメータシートなど)は表計算ソフトが向いています。(あたりまえですね)
また、ワープロソフトやプレゼンテーションソフト内に表を差し込む場合、とりあえず表計算ソフトである程度作りこんで合計などは表計算ソフトの自動計算機能を利用してから差し込むと効率的です。
・プレゼンテーションソフト(Power Point)
このソフトは2つの用途があります。
1つはその名の通りプレゼンテーション資料を作るためのソフトですので、プレゼンテーション用の資料作成にはこのソフトを使用します。
もう1つは「お絵描きツール」としての利用です。各種資料に図や絵を作成する場合はプレゼンテーションソフトで作成してその他のソフトに差し込みます。差し込み方法ですがプレゼンテーションソフトのオブジェクトのまま差し込む方がその後変更しやすくて便利だとは思いますが、イメージ通りに差し込めない場合もあるので私は画面ショットを取って画像として張り込んじゃいます。
・ワープロソフト(Word)
ドキュメントを作成するメインはワープロソフトです。ワープロソフトには自動で目次を作成する機能や見出しの形式(文字の開始位置、大きさ、装飾など)を事前に登録する機能がありますので、それを活用することできれいなドキュメントを作成することができます。
「ある程度のスキル」について
各オフィスソフトについて押さえておきたい「ある程度のスキル」については、上記用途も含め以下の表にまとめました。なお、詳細な操作方法については各種インターネットサイトをご参照ください。
| オフィスソフト | 特徴 | 適用するドキュメント/シーン | 習得すべきスキル |
| 表計算 (Excel) | ・表を作る特に便利 ・合計・平均などの計算も自動でできる ・マスタテーブルを参照することもできる ・タブでページを切り替えられる | ・詳細設計書(パラメータシート) ・問題・課題管理表 (ワープロ/プレゼンテーション資料用の表作成) | ・セルの結合 ・インデント(セル内でもインデントできます) ・合計(Sum)、平均(Ave) ・相対アドレスと絶対アドレス(F4で相対アドレスと絶対アドレスを切り替えられます) ・別表の参照(VLookup) ・最後のセルへ移動するショートカット([Ctrl]+[End]) |
| プレゼンテーション (PowerPoint) | ・絵や図形を作成するのに便利 ・絵や文字などのオブジェクトを自由な位置に配置できる | ・フライヤ ・サービスの紹介資料 ・提案書 (ワープロ資料用の画像作成) | ・マスタプレゼンシートの活用 ・オブジェクトのグループ化 ・オブジェクトの整列/センタリング (自分なりに使いやすいテンプレートを用意しておく) |
| ワープロ (Word) | ・ドキュメント作成ではメインで考えるソフト ・見出し書式や余白の事前設定などで、きれいなドキュメントが作成可能 ・目次の自動作成も可能 | ・提案書 ・要件定義書 ・基本設計書 ・各種手順書/マニュアル | ・見出し設定の活用 ・目次の自動作成 ・ヘッダ/フッタの利用 |
オフィスソフトのオンラインサービスや各種支援ツールが普及し始めた昨今、オフィスソフトを使用する機会も減っていくと思いますが、大手のお客様ではまだまだローカルのオフィスソフトによるドキュメント作成が主流ですので、一度ご自分のオフィスソフトスキルについて棚卸してみてはいかがでしょうか?
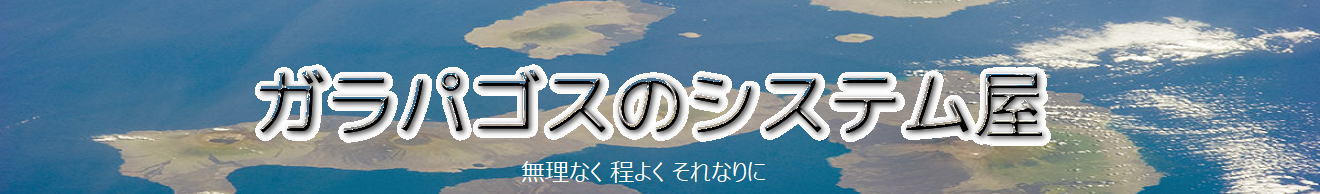



コメント