このシリーズ大変久々ですが、最近感じたことを追加します。
環境変化4:自分のレベルが判りずらい
学生時代というのは言い換えれば、日々競争にさらされていた時代ともいえます。
・定期試験の順位
・通知表の結果
・入学試験の合否
・運動会での徒競走順位
・部活での大会成績やレギュラー争い
・絵画コンクール
などなど日々さまざまな競争が行われ、その結果により自分が集団の中でどのレベルにいるのかを教えられます。自分のレベルを教えてもらうことで「努力するモチベーション」に繋げたり「自分が行った努力の有効性」を検証したりすることができますよね。
社会人に競争があるか?
「社会人に競争があるか?」と問われれば皆さん「そりゃあるでしょう」と答えますよね?
そうです、社会人にはとても厳しい競争がありますしその競争の結果が「待遇」や「収入」に繋がる仕組みになっています。
しかし、問題なのは職種によっては「社会人の競争結果」が非常に見えづらい場合があるということです。もちろん営業職など、日々自分の仕事が数値化されるような職種では競争の結果が明確に示され自分のレベル(順位)が判りますが、我々システム屋のような技術職の場合は競争結果が非常に見えづらいため自分のレベルについてもイマイチ不明確です。
なぜなら、実際の業務で “複数人で同じ課題に取り組み結果を比較する” といったこともほぼありませんし、競争結果が反映される給料を同年代で比べるといったこともありません。
このような状況だと多くの場合人は根拠もなく「自分は平均ぐらいだろ」と思うそうです。「自分は平均ぐらいだろ」という認識を持ってしまった人は、その状況に安住し自分のレベルを上げるための努力をせず言われたことを日々こなすだけのワークスタイルに陥ってしまいます。もちろん自分が本当に「平均ぐらい」であり、そのレベルに納得しているのであればいいのですが、もし本当は「平均以下のレベル」だったとしたら・・・
じゃぁどうするればいいのか?
社会人になったら、積極的に自分のレベルを自分で意識するようにしてください。具体的には・・・
・同世代のできれば同業者と(給料ではなく)仕事について話してみる
・定期的に業界動向を参照し市場価値のあるスキル/ワークスタイルを調査する
・転職エージェントに登録する
といったアクションがあります。
自分のレベルを上げる方法は学生時代から自らの努力のみですが、社会人になったら自分のレベルがどの程度なのかを認定するのも自分自身なのです。

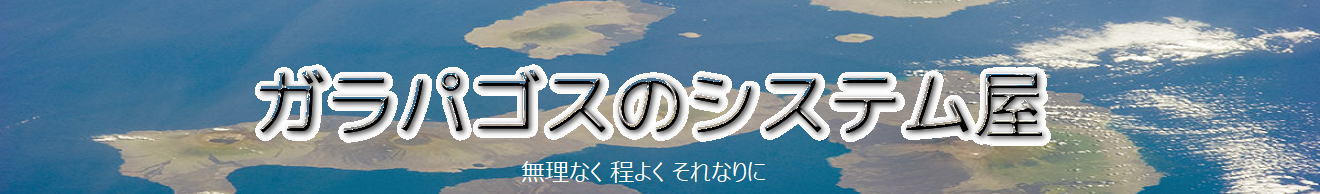



コメント