今回はお客様によって「持っているシステム環境」や「その呼び名や構成」が違うというお話です。
システム環境とは?
ここで言うシステム環境とはシステムが動作するための「場所」です。たとえばサーバーとかOS/各種SWとかネットワークとか、対象システムが動作するために必要となる諸々リソースの集合体といった所でしょうか?
システム環境は通常複数ある
システムを安全に維持管理していくためには、多くの場合「ユーザーが利用する環境」だけでは不十分です。なぜならシステム改修や環境変更の作業を安全に行うことができないからです。言い換えれば「ユーザーが利用する環境」に影響しない別のシステム環境を用意し、そこでシステム改修や環境変更を事前に実施することで本システムの安定的な実現しています。
システム環境の種類
上記のような理由から、通常お客様は1つにシステムに対し複数の環境を保持しています。詳細な説明は各種Webサイトに譲りますが一般的なシステム環境の種類と名前は以下の通りです。
・環境1:本番環境
ユーザーにサービスを提供するための環境です。システムの稼働や設定等に関する作業は通常一部の限られた人のみが担当するルールとなっています。
・環境2:ステージング環境(別名:準本番環境、リハーサル環境など)
本番環境で実施しようとするシステム改修や環境変更の最終確認を行う為の環境です。ステージング環境はOSや各種SWなどを出来るだけ本番環境と同一に維持管理されます。またデータについてもある程度本番に近いデータが用意されています。
・環境3:開発環境(別名:検証環境、テスト環境、ローカル環境など)
本番環境で実施しようとするシステム改修や環境変更のテストを実施する為の環境です。開発環境も基本的には本番環境と同一な状態に維持管理されますが、その位置付けから一時的に本番環境と異なっている場合もあります。
たとえば、OSのバージョンアップを予定している場合、通常本番環境に先行して開発環境でのOSバージョンアップが実施されるため、本番OSのバージョンアップが実施されるまでは開発環境のOSと本番環境のOSはバージョンが異なることになります。
また、システム改修や環境変更が複数予定されており、それらの確認作業が並行して行われる場合は、一時的に複数の開発環境が用意される場合もあります。
何が問題なの?
問題なのはお客様によって本番環境以外に保持している環境の数/種類/名前に違いがある場合があり、かつそれぞれの運用ルールにもお客様毎のローカルルールが存在する可能性があるです。例えばあなたが新しいお客様の担当になり、前のお客様での運用ルールから「ステージング環境からの本番リリース作業は自身で行う」と想定していたが、新しいお客様では自身で行うことはできないルールだったため、スケジュールの遅れが発生してしまった。といった感じです。
担当が変わったら環境と運用ルールの確認を!
このような勘違いを避けるためには、担当が変わったタイミングでシステム環境に関する以下のことを確認してください。
・システム環境はどんな種類があるのか?
・それぞれの名前および目的は何なのか?
・自分が利用できる環境はどこなのか?
・自分が利用できる環境の利用ルール(利用アカウント、利用端末、やっていいこと/悪いことなど)はどのようなものか?
・自分が利用できない環境での作業はどのように依頼するのか?
最初にこのような確認をしっかり行うことで、無駄なトラブルや想定外の作業が発生することを防ぐことができます。是非留意してください。
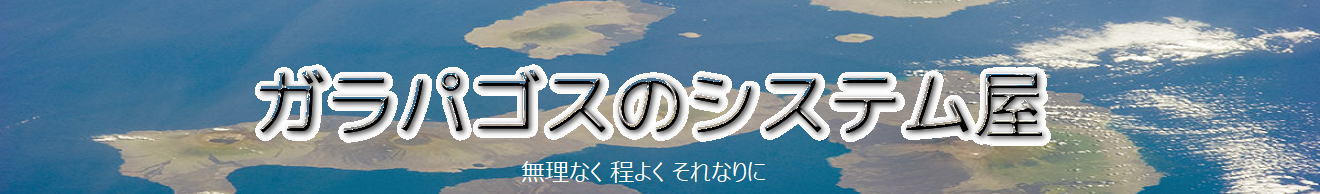



コメント