業界的にはシステム開発の規模を表すのによく工数という道具(言葉)が使われます。
「このプロジェクトにはXX人月の工数が必要」
といった具合です。
でも、この工数という道具はあまり有効な道具とはいえません。なぜなら工数という道具がシステム開発に必要な人財を人数と時間のみで表しているだけで、それ以外の要素を全く示していないからです。
それ以外の要素1:スキル
スキルがある人が1日働くのと、スキルがない人が1日働くのでは成果に雲泥の差がでますよね? 工数の考え方にはこのスキルに関する要素が含まれていません。
そうすると極端な話、10人月の仕事があるとすれば誰でもいいから10人集めれば1ヶ月でその仕事は完了するということになります。そんな上手くはいかないことは、皆さんもご存じですよね。
それ以外の要素2:環境と道具
皆さんが自身の能力を発揮するためには、適切な環境で適切な道具を使えることが(暗黙の)前提条件となっているはずです。この前提条件を謳わずに工数を算出することは、非常に無謀なことです。工数を語る為には「こういった環境でこういう道具が使えること」といった前提条件を明確にしなければ、想定通りの工数で仕事を完了することができないはずです。
それ以外の要素3:コミュニケーションコスト
プロジェクトの人数が増えればそれだけコミュニケーションコストも必要になります。
すなわち100人月の仕事を100人/1ヶ月で実施するのか、10人/10ヶ月で実施するのか、1人/100ヶ月で実施するのかで、コミュニケーションコストはまったく違ってきます。
ですが、このコミュニケーションコストを理解していない人は「人数倍にすれば半分で終わるよね」とか恐ろしいことを思いつくのです。
こんな「使えない」工数ですが、なぜ現在までもシステム規模を表すのに多用されるのでしょうか?それは単に「お客様に解りやすい」からです(笑)
ですので、「工数」という道具でシステム規模を表さなければ場合でも、
・スキル=>要員のスキルレベルを定義する
・道具と環境=>工数算出の前提条件を明記する
・コミュニケーションコスト=>管理工数などの名目で工数を追加する
などの対策をしっかりとって、適切な工数提示を行ってください。そうでないと、地獄を見ることになりますよ。

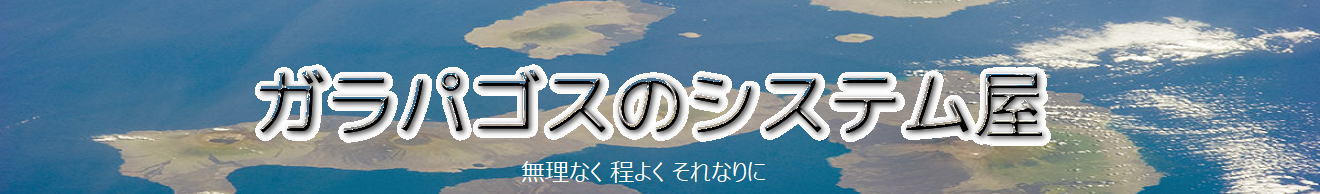



コメント