前回の記事でプロジェクトには「メンバーが合意/共有した目的」が必要と記載しましたが、今回はプロジェクトの目的をどのように検討/定義すればよいか?について記載します。
改めて記載しますがプロジェクトの目的はお客様も含めたプロジェクトメンバー全員で「共有/合意」する必要があります。そうでないとメンバー個々が色々な方向に向かってしまい皆の力が目的に向かって集中ぜず効率の悪いプロジェクトになってしまいます。
逆に言えばプロジェクトメンバー全員で目的を共有/合意できれば、非常に高い確率でプロジェクトは成功します。(イヤ、ホントに)
共有/合意できるプロジェクトの目的とは?
メンバー全員で共有/合意出来づらい目的を「悪い目的」、共有/合意しやすい目的を「良い目的」として、まずは「悪い目的」の記載例を以下に記載します。
(悪い目的の記載例)
・社内における情報共有を活性化する
・XXサービスの可用性を向上する
・XXXシステムをクラウドサービスに切替る
いかがでしょうか? 何となくマズそうな雰囲気を感じていただけたでしょうか? それでは次に「良い目的」の記載例について以下に記載します。
(良い目的の記載例)
・情報共有スピードアップのため、外出先からでもメールが確認できるようにする
・XXサーバーを冗長化しサーバー障害時のダウンタイムを30分以内にする
・XXXシステムをクラウドサービスに切替ることで維持管理コストを20%削減する
どんな違いがあるかご理解いただけたでしょうか?
以下に「良い目的のポイント」を記載しますので、改めて「悪い目的」と「良い目的」を見比べてみてください。
・目的達成前後の違いが明確になっている
・目的の達成が客観的に評価できる。
・目的の達成で得られる効果が明確になっている
本来であればプロジェクトの目的はプロジェクト開始前に「良い目的」として定義/共有/合意されている必要がありますが、初期段階ではまだ「悪い目的」のままのケースもあります。
プロジェクトに参画する際、まずは「プロジェクトの目的がどのように定義されているか?」を確認していただくと共に、もしその目的が「悪い目的」であればできるだけ早急に「良い目的」に再定義するようにしてください。
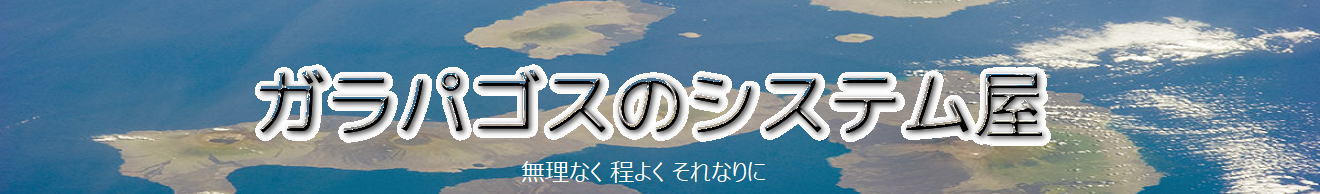



コメント