貴方がもしSIベンダー等で働いており、様々なお客様のプロジェクトを担当するというワークスタイルであるとすれば、プロジェクトに関する様々な事柄について「お客様によって考え方に違いがある」ことを認識しておく必要があります。なぜならお客様の考え方を認識していないだけで大きなトラブルに繋がるケースもあるからです。
・なぜ、お客様の考えは認識しづらいのか?
お客様は通常自社のプロジェクトしか担当しませんから「お客様の考え」はお客様にとって「常識」であるため、たとえ自社のプロジェクトに初参画するベンダー向けだとしても積極的に開示することがありません。そりゃそうですよね、だって「常識」なんだもん(笑)
そんな一歩間違うと大惨事に繋がる「お客様による考え方の違い」について、今回以降シリーズでお話したいと思います。
フェーズに関する考え方
お客様によって違うフェーズに対する考え方に違いがあります。
タイプ1:上位フェーズでの成果物の変更を基本的に許さないお客様(後戻りNGタイプ)
例えば基本設計フェーズで作成した基本設計書はフェーズ終了時点でレビュー&承認されますが、それを以降のフェーズで変更することは「基本的にNG」と考えるお客様がいます。(まぁ不可能という訳ではないですが)
正論ではあるのですが、そうはいっても現実問題として詳細な設計やテストを行っていく上で、基本設計の内容を修正せざる得ない場合もありますので、そうなるといろいろとメンドクサイ(変更理由の明確化/文書可、影響範囲に関する調査報告書の作成や役職者を集めた再レビューなど・・・)ことになります。
なのでこのようなお考えのお客様の場合の対策としては、フェーズ毎に作成する成果物の記載粒度は後続フェーズで変更されることない程度のレベルに留めるという方針が妥当ということになります。
具体的には上位フェーズでの成果物については、後々変わることがないレベルの内容を「フワ~~~」と書いていておいた方が無難です。
タイプ2:上位フェーズでの成果物の変更を柔軟に考えるお客様(後戻り容認タイプ)
こちらのお客様の場合は各フェーズの成果物の記載内容についてあまり神経質にならず、必要と思うことを必要と思う粒度で記載してOKです。ただし仮に変更が発生した場合は、影響調査を行った上で変更履歴はちゃんと記載しましょうね。
もちろん「タイプ1」がダメで「タイプ2」が正しいという訳ではないのですが、「タイプ2」だと思っていたら実は「タイプ1」だった場合、結構洒落になりませんのでできるだけ早期にお客様の「フェーズに対する考え方」を確認し、適切な対応を取るようにしましょう。
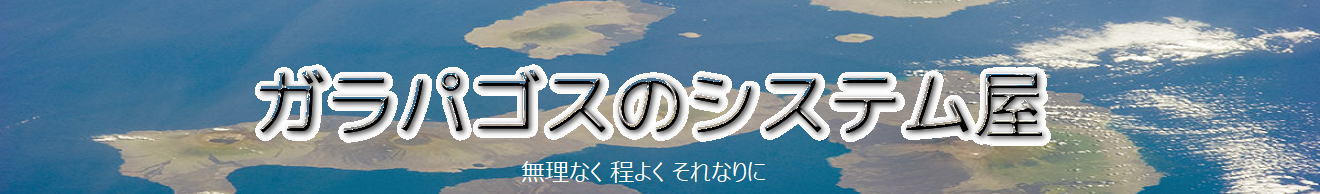



コメント