最後のステップはいよいよ「3. プロジェクトスケジュールの立案」です。
「2. リリースまでのタスク明確化」でやるべきタスクと工数が明確になったら、それらを繋げてスケジュールを立案します。
3. プロジェクトスケジュールの立案
このステップではプロジェクトの実施スケジュールがアウトプットとなるわけですが、単純にタスクを繋げるだけでなく考慮するべき点が幾つかありますので、その内容をこの記事では記載しますね。
また、後述の内容をお読みいただければご理解いただけると思いますが、プロジェクト体制についてもアウトプットなります。(体制を想定しないとスケジュールは組めないでしょ?)
1: プロジェクト体制の想定
まずはプロジェクトを進める上での体制を想定します。このタイミングでアサインできる人が全て明確になっていればいいのですが、そうでないケースがほとんどなので他プロジェクトなどの実績を参考にプロジェクトメンバーの人数と大まかな役割を想定します。
2: タスクの依存関係の考慮
タスクには通常依存関係がありますので、依存関係を意識したスケジュールになっている必要があります。依存関係を表すにはパート図(アローダイアグラム)が向いています。
3: 外的要因の明確化
スケジュールにインパクトを与える外的要因が明確化します。たとえば機器の納品や関連システムの対応などがそれにあたります。外的要因についてはこちらが期待するスケジュール感に対し問題ないかを確認すると共にリスク項目にも挙げておきます。
4: プロジェクト要求スキルの明確化
プロジェクトの実施に必要となるスキル項目を洗い出します。この洗出しについても何人かの人に協力を要請し、ブレスト形式で行うことをお勧めします。ブレストについては以下のリンクおよび各種インターネットサイトをご参照ください。
ブレストできるようになろう!
5: スキルホール有無の確認
プロジェクトの要求スキルの中に獲得が難しいスキルがある場合は、そのスキルに対する対応も考えスケジュールに反映します。
たとえば利用するMWに対するスキルの獲得が難しい(社内で扱ったことのないMWの場合や、扱ったことはあるけれどプロジェクトではその最新バージョンを利用するとか・・・)場合は、予め担当者を任命して社外研修や検証環境での動作確認など、スキルを獲得してもらうためのタスクを追加するといったイメージです。詳細については以下のリンクをご参照ください。
スキルマップの作り方
数回にわたりプロジェクト計画について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか?
たくさんの留意点や考慮点がありましたが、これらの1つ1つを出来るだけ早急に明確化していくことができればプロジェクトの成功へ繋がっていくことと思います。
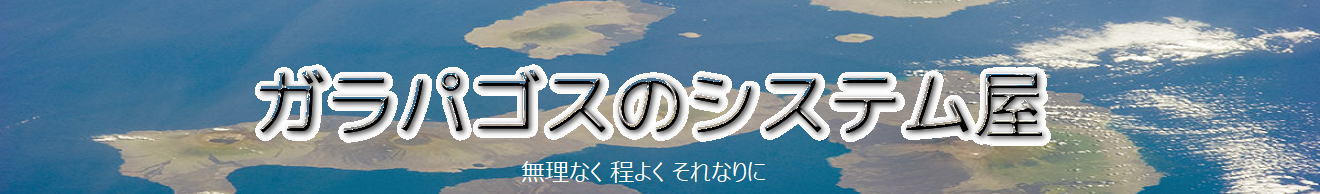



コメント