前回記載したように、「スケジュール立案の前には、各種影響要因について想定する必要がある」とすれば、プロジェクトスケジュールの立案作業はプロジェクト全体を計画する(いわゆるプロジェクトプランニング)と同値であることにお気づきになると思います。
ですので、この記事ではプロジェクト計画の策定方法について記載したいと思います。これから記載するプロジェクト計画のためのタスクを順次・確実に実行することで、前回記載した影響要因に対する対応ができるとイメージしていただければよいかと思います。
プロジェクト計画の流れ
プロジェクト計画は大きく分けて以下の3ステップで行います。
1. リリース後イメージの明確化
システムがリリースされた後のイメージを明確化します。システム構成だけではなく運用についても明確化しましょう。
さらには、ユーザー教育や移行作業といったシステムリリース時のイメージについても明確にする必要があります。
2. リリースまでのタスク明確化
リリースまでに必要なタスクおよびそのタスクに必要となる工数について明確化します。
必要タスクの中には間接的な作業も含まれますので見落とさないようにしてください。
また、工数についてはアサインできるメンバーのスキルやお客様の作業ルールに左右されることがあるのでその辺りについても考慮が必要です。
3. プロジェクトスケジュールの立案
上記の内容が有る程度明確化されてから初めて、プロジェクトスケジュールの立案が可能となります。もちろんプロジェクトの初期段階で全ての項目について明確化できない場合も多いですが、少なくとも立案時点で可能な項目についてあの手この手で明確化することを怠らないでください。ここで手を抜くと後で手痛い「しっぺ返し」を食らうことになりますよ。
次回以降で各ステップの詳細な内容について記載したいと思います。
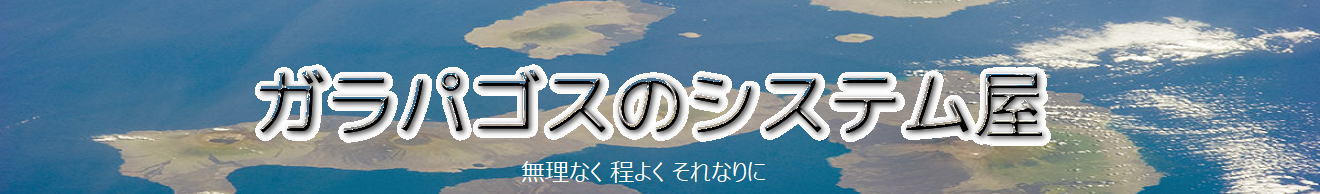



コメント