前回お知らせした「人が壊れるマネジメント」という本を読んだ感想を、今回から数回に分けて記載したいと思います。
「アンチパターン01:タスクを丸投げされて壊れる」の感想
確かに配慮の無い上司から、いい加減にタスクを振られると精神的なダメージを受けますよね。本書では「指示が曖昧な状態でタスクを進めると、担当者は何を求められているのかが正確にわからないため、必然的にアウトプットの品質がタスクを指示した側から見て不十分なものとなることがしばしばあります。」と記載されていますが、全くその通りだと思います。
本書では「タスクを丸投げ」しないための解決策として「タスク依頼時には”6W2H”を意識する」としていますが、これにはちょっと疑問を持ちました。
“6W2H”といえば、「何(What)を、何のために(Why)、誰が(Who)、誰に(Whom)、どこで(Where)、いつまでに(When)、どのように(How)、どれだけ(How much)やるべきなのか」ということになります。
確かにそこまで細かく説明すれば「丸投げ」に比べて適切な質/量のアウトプットが期待できると思いますが、
・ タスク依頼元の負担が大きい
・ タスク依頼先(作業者)の工夫の余地が狭まる(スキルがアップしずらい)
といったデメリットがあると思います。
実際、現実のプロジェクトではタスク依頼先よりタスク依頼元の方が多忙な場合がほとんどだと思われるので、タスク依頼元の負荷が極端に上がるようなアプローチは現実的ではない気がします。
じゃぁ、どうするのか?
以前の記事でも記載したとおり、私の考える対応策はタスク依頼先(作業者)に「後続作業を認識してもらうこと」です。
(関連記事:環境の激変を認識せよ(3):アウトプットの意識)
このアプローチであれば、
・タスク依頼元の負荷はあまり上がらない
・タスク依頼先(作業者)は後続作業を知ることで「求められている質/量」についてはある程度できる(適切なアウトプットを期待できる)
・タスク依頼元から細かいやり方を指示されないので、作業者自身で創意工夫する必要がある(スキルアップにつながる)
というカンジになると思います。
もちろん、タスク依頼先(作業者)のスキルレベルによっては”6W2H”による丁寧な作業指示が必要な場合もあるとは思いますが、作業者がやる気をもってタスクを実施してもらうためには、自ら情報を集め、創意工夫していく余地を与える事もマネジメントとしては大切な事だと思いますよ。

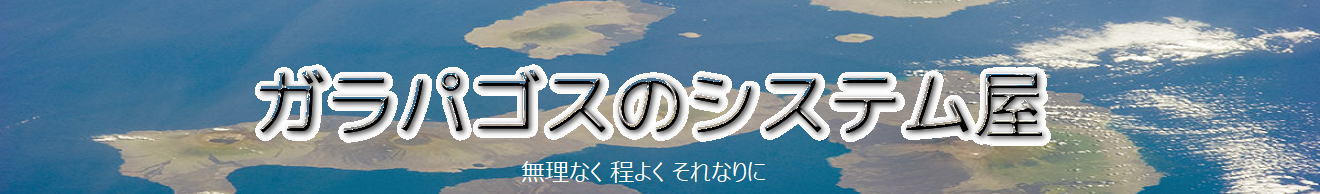



コメント