世に「失敗プロジェクト」というのは沢山ありますし、皆さんの中でも「参加したプロジェクトが失敗して酷い目にあった」という経験をされる方もいらっしゃると思います。
プロジェクトには一般的に「新規プロジェクト」と「継続プロジェクト」というのがありますが、失敗する確率が格段に高いのは「新規プロジェクト」です。
「失敗する確率が格段に高い」と書きましたが、実際はタイトル通り「新規プロジェクトは必ず失敗する」といってもいい程です。
なぜ、「新規プロジェクト」は必ず失敗するのか?
「新規プロジェクト」がなぜ必ず失敗するのでしょうか? それは比較的失敗することが少ない「継続プロジェクト」との違いを考えれば明確になります。
「継続プロジェクト」との違い
「新規プロジェクト」と「継続プロジェクト」の大きな違いは、お客様との共通認識があるか、どうかということです。すなわち「継続プロジェクト」では、それまでの作業を通じてお客様との共通認識が構築済みです。その共通認識を前提に作業を実施することから失敗する確率が格段に低くなります。
一方「新規プロジェクト」ではこれらの共通認識が無い状態で作業を進めることになるので、不適切かつ非効率な作業となってしまいトラブルに発展(失敗)してしまうのです。
それなら新規プロジェクトであってもまずは共通認識を構築してから作業すればいいんじゃないかと思いますよね? その通りです。しかし実作業前の共通認識構築を阻む要素が以下の2点です。
・ システム屋の不明確な成果物
・ 人の思い込み
システム屋の不明確な作業内容や成果物
例えば、建設業では沢山の人が協力して「建物の建築」という新規プロジェクトを推進しているわけですが、こちらはほとんど失敗しません。これは「建物の建設プロジェクト」の作業(タスク)については、その作業内容や成果物が明確に定義されていることに起因しています。たとえば設計作業の場合成果物となる設計書は書式や粒度が明確に定められていますし、そもそも設計を行う人(建築士)は国家資格を有する人が担当します。これは「作業開始前からプロジェクト全体で共通認識が構築済みの状況」であると考えられます。
一方システム屋の設計書はある程度のガイドラインはあるにせよ、明確なフォーマットや粒度の定義は標準化されておらずある意味「書く人の経験と力量」次第になってしまいます。そのため作成された設計書を受け取ったお客様から「内容が適切でない」「想定していたものと違う」「フォーマットが違う」といったクレームに繋がってしまうことにもなります。
人の思い込み
人は自分の認識・感覚を「一般常識」と考える傾向があります。それはシステム屋である貴方もそうですし、お客様も同じです。特にお客様は自社の環境、ルール、お作法のみしか知らないことから、それを「一般常識」と考えがちで、共通認識を事前にすり合わるという意識をお持ちいただけないケースがほとんどです。(だって我々は標準的なルールのプロジェクトを行うんだから・・・)
うーん、困りましたね。このまま記事を終わってしまうと「新規プロジェクトは必ず失敗する」ことへの対応方法は “ない” ことになってしまいます。
確かに全く失敗なしに新規プロジェクトを実施・完遂する方法は “ない” とは思いますが、次回できるだけ早い段階で共通認識を構築して、新規プロジェクトの失敗を最小限に抑える方法についてお話したいと思います。
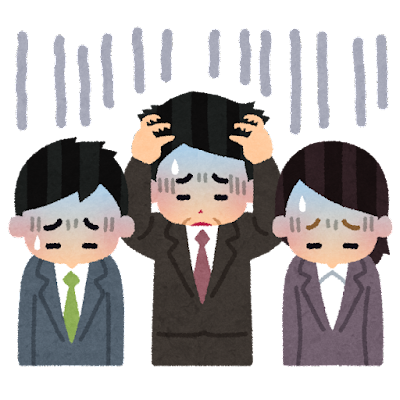
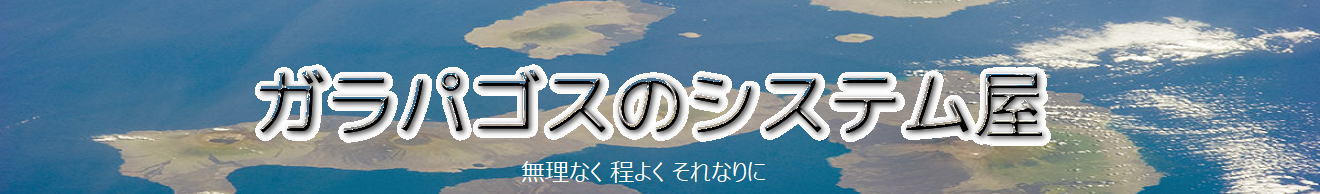



コメント