逆説的ではあります、スケジュール立案を行う前に、まずは「スケジュールに影響を与える要因」について見ていきましょう。すなわちスケジュールの立案はこれらの要因に対し「妥当な想定」を行った上で行う必要があるということになります。
スケジュールに影響を与える要因
要因1:工数の見積りミス
「思ったより工数がかかった」というヤツです。このような事態を防ぐために「類推法」や「FP法」などなど星の数程の手法が存在しますが、実際のスケジュール立案にあたってこれらの手法は「あんまり重要ではない(役には立たない)」と私は感じています。なぜならスケジュール超過が発生する要因は単なる工数の計算ミスではなく、後述する要因による場合はほとんどだからです。
「類推法」「FP法」などエライ先生が考えたカッチョイイ手法について私は、お客様に対し「見積もり根拠を示すため(ダケ)の道具」という捉え方をしています。
要因2:前提事項の変更
プロジェクトはいろいろな前提条件を元に作業を進めていきます。プロジェクト見積もり段階で設定/想定した前提条件が変更されることでスケジュールに甚大な影響を与えることが多々あります。
前提条件については「事前に合意していたにも関わらず変更される」ケースもありますが、最も多いのが「スケジュール立案者が勝手に想定した前提条件がフタを開けてみると違っていた」というケースです。前者であればお客様にスケジュールの変更等のお願いをすることも可能ですが、後者の場合はスケジュールの変更は難しくトラブルプロジェクトとなってしまう確率がグンと上がります。
要因3:追加タスクの発生
プロジェクトが進んでいく中で想定していなかったタスクがポコポコ発生するケースです。他の要因の影響で発生する場合も多いですが、そもそも「そういわれてみれば必要だね」となって発生するケースも結構多いです。(困ったモンだね)
要因4:要件の追加・変更
おなじみのヤツですね。要件の追加や変更があればスケジュールに影響が出るのは当然です。もちろん簡単に受け入れることはできないですが、内容や状況によっては受入ざる得ない場合もあります。
要因5:タスクの依存関係の問題
「あっちタスクが終わってないからこっちタスクが始められない」という状況です。このような事態が発生すると人員的には十分であってもスケジュールに影響が出てしまいます。
要因6:アサインメンバーのスキル
大抵の場合、必要工数に見合う人員(いわゆるアタマカズ)はそれなりに用意されますが、そのメンバーがプロジェクトに必要とされるスキルを持っているとは限りません。プロジェクト全体におけるスキル不足(スキルホール)の存在は非常に危険です。なぜならスキルがあれば10分で済む作業も「スキルが無かったから1週間掛かってしまった」というケースはザラで、そんなことが重なればスケジュールなんてすぐに崩壊してしまいます。
要因7:外的要因の影響
プロジェクトの進行はプロジェクト外の様々な要因に左右されることがあります。たとえば「使用する機器の納品」や「連携システム側の対応」といった物。
外的要因はプロジェクトのコントロール下に無いので、当要因に関するトラブルへの対応ば非常に難しくなる傾向にあります。
いかがでしょうか? プロジェクトって危険がいっぱいですね(笑)
でもビビらないで下さい。次回以降の記事ではこれらの要因への対処方法について見ていくことにしますので。(^▽^)/
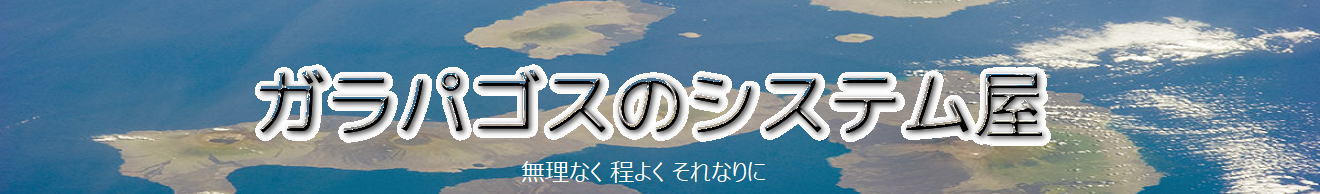



コメント