久々にこのシリーズの追加記事になります。今回はお客様によって「テストのやり方」および「テスト結果のまとめ方」が違うというお話です。
テストのやり方
テストのやり方については概ね以下の2タイプがあります。
(タイプ1) テストの担当者が1人で実施する
(タイプ2) テストの担当者が実施している内容をもうひとりの人が確認する(いわゆる再鑑)
もちろんコストの面を考慮すると当然(タイプ2)の方が割高になります。
お客様によって「テストといえば当然タイプ2のように実施するものである」と認識している場合もありますし、他のお客様では「実施方法はベンダーにお任せする」という場合もあります。
また「単体テストは(タイプ1)で、結合テスト移行は(タイプ2)で」などフェーズによって(タイプ1)と(タイプ2)を使い分ける場合もあります。
テスト結果のまとめ方
テスト結果のまとめ方についても概ね以下の2タイプがあります。
(タイプ1) テストケースにチェックを付けるだけ
(タイプ2) テストケースにチェックを付けるとともに、テストが正常に行われた証跡(画面ショットやログファイルなど)も取得する
どちらの方が工数がかかるかといえば、当然(タイプ2)です。つまり、こちらもコストの面では(タイプ2)の方が割高になります。
「テスト結果のまとめ方」についても、お客様が「当然タイプ2のことである」と認識している場合もありますし、「テスト結果は(タイプ1)で十分ですので、その前提で工数を見積もってください」という場合もあります。
お客様はなぜ(タイプ2)を選ぶのか?
「テストのやり方」「テスト結果のまとめ方」のどちらも、テスト品質という点では(タイプ2)の方が高くなる傾向にあります。しかし(タイプ1)と比較して(タイプ2)はコストが2倍以上になり場合もあることから、費用対効果という観点では必ずしも良い選択だといえません。
本来であれば対象となるシステムの重要性や掛けられるコストに応じて(タイプ1)と(タイプ2)を使い分けるべきなのですが、お客様担当者が「システムの重要度」を適切に判断できないケースも多く、とりあえず盲目的に(タイプ2)を求めているというケースが少なくありません。もしくはそもそも(タイプ1)のようなやり方があることを知らないということもあります。
見積前に確認を!
一番不幸なケースは、「テストのやり方」「テスト結果のまとめ方」がどちらも(タイプ1)だと思って見積もったのに、実際お客様想定していたのはどちらも(タイプ2)だったというケースです。
お客様としても「テストのやり方」「テスト結果のまとめ方」はシステムに品質に関わる部分だと認識しているので、簡単に引き下がってはくれません。結局ほとんどのケースでシステム屋が泣くことになります。
そうならない為に見積前にお客様の想定する「テストのやり方」「テスト結果のまとめ方」を必ず確認してください。そのプロジェクトに参画してくれるメンバーの幸せの為に(笑)
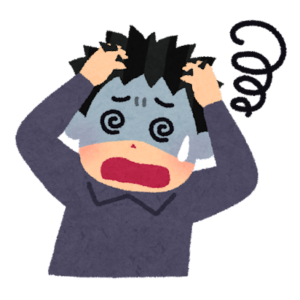
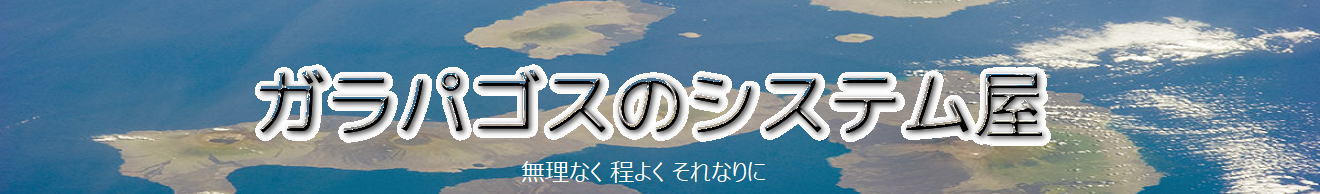



コメント