当テーマの6回目です。(1回目、2回目 、3回目 、4回目 、5回目 )
プレゼンテーション資料のチェックポイント
・ターゲットの判断基準を知る
ターゲットの判断基準を知ることは非常に重要です。ターゲットの判断基準に従いプレゼンテーションを組み立てることで、成功の確率は大きく上がります。難しいケースも多いですが、できる限りこの情報を取得するようにしてください。たとえば組織内での立場や役割に関する情報は非常に参考になります。
・情報収集する
資料を作成するにあたりできる限り情報収集を行ってください。必要な情報が収集できない状態で資料を作成すると、品質が著しく劣化するとともに作成に余計な時間がかかります。どうしても情報が不十分の場合は、プレゼンテーションを2回に分け、1回目(ヒアリングを中心としたプレゼン)、2回目(行動変化を狙うプレゼン)とする場合もあります。
・ウソは絶対にダメ
記述内容にウソがあり、それが聞き手に見抜かれてしまえばその先話を聞いてもらうことできません。 もちろん信用はなくなり、回復することはほぼ不可能です。ただし、不確かなことを記述しなければならない場合もあるので、その時は「不確かである」ことを明確に記載します。
・書き手の「考え」や「感想」は隠して記載する
求められない限り、書き手の「考え」や「感想」は記載しません。もちろん書き手の「考え」や「感想」は必要ですが、「私はこう考えます」といった直接的な記述ではなく「客観的事実の積み重ね」や「有識者の意見」で間接的に自分の考えを伝える必要があります(これはかなり高度なアプローチですが非常に重要です)
・1ページのまとまりに気を遣おう
1ページ内に収める情報のまとまりに気を使いましょう。内容にもよりますが基本1ページには1メッセージであることが好ましいです。聞き手は、「ページが切替わる事」=「内容が切替わる事」と捉えらてしまいがちです。
・枚数に気を遣おう
余程興味がある内容でもない限り、枚数が多いと途中で聞き手の集中力がなくなってきます。可能な限り10枚以内でまとめるようにしましょう。但し最初から10枚以内に纏めるのではなく、まずは書けるだけ書いた上で、不要な部分や冗長な部分をそぎ落とし、10枚以内にしていきます。あなたが「書きたい情報か?」より聞き手が「聞きたい情報か?」を考えてください。どうしても枚数が多くなってしまう場合は、最初に全体像(目次など)を説明し、5-6枚毎に「いまどこの部分を話しているかの説明」や「これまでのまとめ」を挟みましょう。説明するかどうか迷うような内容については、「参考資料」として最後に記載しておき、必要に応じて説明するようにします。
・“美しさ”も技術のウチ
内容が素晴らしくても、文字の開始位置がずれていたり、フォントがパラバラだったりすると、資料の価値は大きく下がってしまいます この程度のことで無駄に評価を下げないよう、美しさにも気を使いましょう
・フレームワークを使う
世の中には先人の方が開発した様々なフレームワークがあります。これを活用しない手はありません。フレームワークは検索すればいっぱい出てきますし、気に入った物は自分のストックとしてためておきましょう。
・絵を書こう
絵を書くのは文字を書くより何倍も時間がかかりますし、その分労力も必要です。しかし、的確な絵の効果は絶大で、文字が無くてもスムースに情報伝達できる場合がほとんどです。億劫がらずに、できるだけ絵を書くようにしてください(訓練でいくらでも上達します)
・寝かせる
完璧に書き上げたつもりの資料でも、時間が経って(寝かせて)から読み返すと必ず改善点が見つかります。ですから時間をかけて完璧に仕上げるより、不十分でもいいのでなるべく早く全体を完成させ、時間をおいて何度か見直し、完成度を高めていく方法をお勧めします。
・レビューしてもらおう
自分の作成した資料を自分で客観的に評価することは非常に難しいことです。できる限りレビューしてもらいましょう(ただし、レビュー結果をすべて資料に反映する必要はありません)
(つづく)
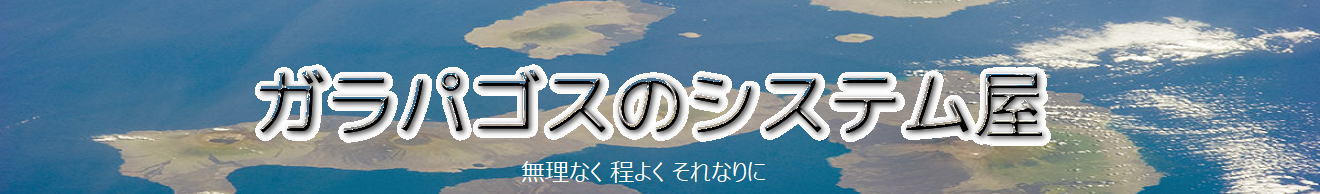


コメント